AI時代における薬剤師の価値とは カケハシ「Pharmacy Leaders Day2025」開催レポート
- ito397
- 2025年7月28日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年7月29日

電子薬歴システム「Musubi」をはじめとする薬局向けソリューションを展開するヘルステックスタートアップの株式会社カケハシは、7月24日に薬局DXをテーマにしたカンファレンス「Pharmacy Leaders Day2025」を東京都内で開催した。
開会にあたり挨拶に立ったカケハシの中尾豊社長は、このイベントを2021年に初めて開催した当初は5年後10年後の薬局経営や業界がどうなっていくのかを情報提供する趣旨だったが、近年AIの普及技術的な変化が激しいため、今年来年の変化を把握してどう生かしていくかが喫緊の課題になっていると述べた。
周知のとおり、近年劇的な勢いでAIが普及してきており、あらゆる産業分野から私たちの身近なライフスタイルに至るまで大きな変革が起こりつつある。そのような状況を背景に薬局・薬剤師の業務や働き方にどのように影響が起こってくるのか。「進化する薬局DX ― AI×データ時代における「患者のための薬局」とは」と掲げられたテーマに沿って、医療DX、AI分野の専門家から薬局のDXに実践する薬剤師による講演やシンポジウムが行われた。
地域医療における薬剤師の活躍への期待 ~患者モニタリングの価値~
厚生労働省 松下俊介氏

厚生労働省の松下氏は少子高齢化が急速に進むうえで、生産人口が劇的に減少する段階に入っている現状に触れ、コンビニよりも多い薬局店舗数と30万人いる薬剤師人口について「多いからこそできることがある」として、調剤にとらわれず、医薬品周辺に関わる多彩な活躍をすることに期待を込めた。半面、外来調剤は2025年がピークで、外来調剤はこの先シュリンクしていく市場である。第6次医療計画に沿って在宅医療への参画が求められる中、居宅訪問管理指導が増えている統計があるものの、しかし現状では登録だけしかされておらず在宅医療の本質的な役割が果たされていないという見方も示した。
“薬局・薬剤師の存在価値”の再定義 − PHR・EHR時代の薬剤師の介入と地域包括ケアへの参画 −
秋田大学医学部附属病院 岡崎光洋氏

岡崎光洋氏はPHR・HER(※)時代の薬剤師として講演をおこなった。いまから15年後の2040年頃の人口構成を考えた場合、日本国内でも地方によって患者数や医療資源が異なるため課題も異なることを指摘。医療資源の少ない地方での医療DXによるサポートの一例として、医療MaaSという移動式診療カーとオンラインシステムを組み合わせた事例を紹介。またこれから求められるものとして、PHR・EHRを活用して患者ごとのデータを解析するなど、画一化された医療ではなく個別化した医療の実現が必要であると述べた。また地域包括ケアシステムにおける地域のことを「感情共同体」であると定義。薬剤師は地域の多職種連携の中でハブ的な存在になることに期待を込めた。
※Personal Health Record … 個人の健康や身体の情報を記録した健康・医療・介護関連のデータ。 Electric Health Record …医療機関などで取得される診療情報や検査データ、既往歴やアレルギー情報などを共有する仕組み。
AIの進化が変える患者体験 医療・ヘルスケア分野におけるデータ駆動型アプローチの展望
千葉大学大学院医学研究院/数理創造研究センター・生命医科学研究センター 川上英良氏

川上英良氏はもともと人工知能を学びたくて医学部を志したという経歴の持ち主(しかし入学当時の2000年初頭のAI研究は下火で苦節の時期を過ごしたという)。AIの普及によって従来の標準治療から個別化医療の時代に変わっていくと説明。また実はAIは共感的コミュニケーションにも強く、医療相談でも医師よりもChatGPTのほうが患者の評価が高かったという調査結果があることを報告した。このほか医療の世界で起こっているAIによるパラダイムシフトの例として、画像診断の解析精度の向上や、蓄積した患者データからシュミレーションすることで起こりうる症状の予測や早期発見ができるようになったこと、精度の高い薬材投与量の設定ができるようになったことなどを紹介した。AI時代の薬局においては医師が着手できていないような患者のウェアラブル端末などのデータ活用などで期待できると述べた。
ビッグデータの活用で明かす「薬剤師の価値と貢献」
岡山大学学術研究院/九州大学システム情報科学研究院 濱野裕章氏
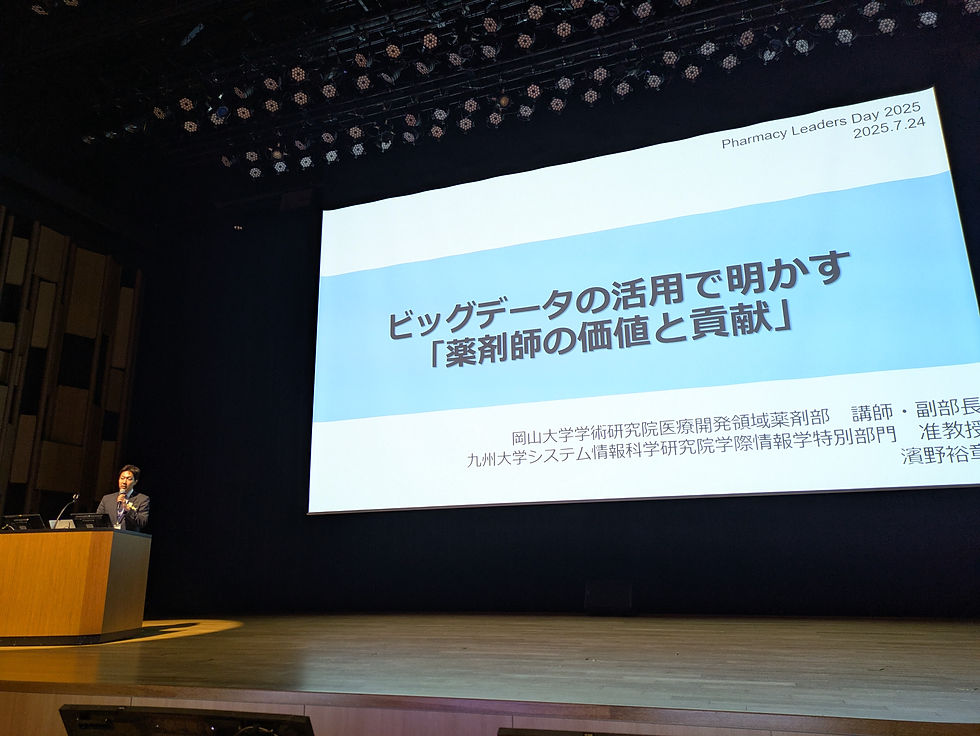
濱野裕章氏はビッグデータ時代の薬剤師の価値について講演。ビッグデータを使いこなしていくためにも薬学生から教育していく必要があると述べた。薬剤師の価値は、従来は調剤などの技術を競ってスピーディーに作業ができることが評価されていた時代から、AIを駆使して情報を組み合わせて活用することができるかどうかに価値が問われる時代になると説明。薬剤師が医療情報データベースと生命科学データベースを活用することで治療の質の向上や副作用の低減、また地域医療でもセルフメディケーションへの貢献ができる取り組みを紹介した。薬局でカケハシの「Musubi」が活用されることで、医療データベースが作り上げられていることも触れ、薬剤師の介入による医療の質向上を経済効果として可視化することにもつながると述べた。
パネルディスカッション:情報技術は「患者のための薬局」をどう変えるのか
千葉大学大学院医学研究院 川上英良氏
岡山大学学術研究院 濱野裕章氏
株式会社グリーンメディック 多田耕三氏
ファシリテーター:株式会社カケハシ 鳥越大輔氏

パネルディスカッションでは川上氏、濱野氏に加え、大阪府豊中市を中心に開局する株式会社グリーンメディックの多田耕三代表が加わり、カケハシのエンジニアリング事業部でデータ&AI部門長を務める鳥越大輔氏がファシリテーターを務め、改めて今回の主題である「情報技術は薬局をどう変えるのか」についてそれぞれの意見を展開した。
多田氏は“ITオタク”を自称して薬局経営においても開局当時からシステム化に力を注いできた。在宅医療業務の社内情報共有の効率化を目的に、スケジューラーを基軸にMusubiと、画像でマニュアルをAI生成するアプリを組み合わせてスタッフとの分担を情報連携を確立し、採算性を高めている実績を紹介。AIについては「破壊的イノベーション」との認識を示し、業務効率化などに貢献することは認めつつも、しかしさらに地域医療において薬剤師として新しい市場の創造に繋げられなければ(将来性は)難しいことになる、と述べた。
AI時代の人間のやるべき仕事、専門家としての薬剤師の可能性については、三氏がそれぞれ意見を述べた。
・AIの普及によって大学病院でなくても日常からデータを集めた研究ができるようになり、それを服薬指導などに活用できるようになる。(川上)
・これからはデータ活用が必要と言いながらも、長年調剤を主にやってきた薬剤師が変化することが障壁となる。またデータ活用がマネタイズできるのかも課題が残る。(多田)
・ビッグデータ活用が出そろい活用できる時代になり、一部の人間がつかうのでは無く、薬剤師がみな考えて活用することに期待を寄せ、セルフメディケーション分野に可能性がある。(濱野)
KEYNOTE
株式会社カケハシ 代表取締役CEO 中川貴史氏

締めくくりにカケハシの中川貴史CEOがプレゼンテーションを行い、DXの進展で環境変化の著しいなか、医療業界で今起こっていること、これからのカケハシが開発するプロダクトの方向性が示された。
MusubiにもすでにAIエージェントを搭載することで薬剤師の業務支援に貢献している。
この先、クラウドやセンターで事務も効率化でき、ロボットが調剤を行うことも現実化しているが、オンライン化が進む中では患者の傾向も変化していき、自分に合った薬剤や専門性の高い薬剤師への相談を希望する患者も増えるかもしれない。薬剤師の働き方も、薬局の中に閉じない世界観になることを示した。そして、治療薬を扱うのみならず患者の生活を支えることが薬局の価値となり、テクノロジーの力を借りながら薬局がそれをどう実現していくかが重要なテーマになってくると締めくくった。






コメント